【税理士監修】相続税の早見表(最新)相続税の計算方法や特例・控除もすぐわかる!
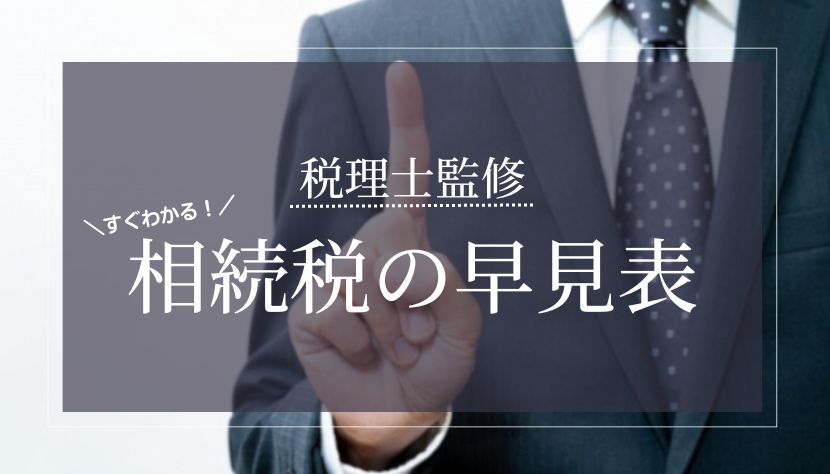
相続が発生し、相続税がどれくらいの額になるのかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、以下の2パターンに分けて相続税の早見表を用意しています。
| ①配偶者と子どもが相続人の場合 ②子どものみが相続人の場合 |
また、相続税を軽減できる主な特例・控除も解説するので、相続税を抑えたい方はぜひ参考にしてください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税の早見表の見方
相続税の早見表は、以下の2パターンのうち自身の状況に適したほうを参考にしてください。
| ①配偶者と子どもが相続人の場合 ②子どものみが相続人の場合 |
前提として、いずれの場合もおおよその相続税額を示すものです。
相続税はさまざまな要因で増減するため、実際の納税額はこの限りではありません。
正確な税額を把握したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続税の早見表①配偶者と子どもが相続人の場合
| 遺産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
| 4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
【例】遺産総額5,000万円の相続税額
遺産総額が5,000万円で、配偶者と子どもが相続人の場合の早見表は以下の通りです。
| 配偶者と子1人 | 385万円 |
| 配偶者と子2人 | 315万円 |
| 配偶者と子3人 | 0円 |
| 配偶者と子4人 | 0円 |
【例】遺産総額1億円の相続税額
遺産総額が1億円で、配偶者と子どもが相続人の場合の早見表は以下の通りです。
| 配偶者と子1人 | 40万円 |
| 配偶者と子2人 | 10万円 |
| 配偶者と子3人 | 262万円 |
| 配偶者と子4人 | 225万円 |
相続税の早見表②子どものみが相続人の場合
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
| 4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
※法定相続分で相続した場合
【例】遺産総額5,000万円の相続税額
遺産総額が5,000万円で、子どものみが相続人の場合の早見表は以下の通りです。
| 子1人 | 160万円 |
| 子2人 | 80万円 |
| 子3人 | 20円 |
| 子4人 | 0円 |
【例】遺産総額1億円の相続税額
遺産総額が1億円で、子どものみが相続人の場合の早見表は以下の通りです。
| 子1人 | 1,220万円 |
| 子2人 | 770万円 |
| 子3人 | 630万円 |
| 子4人 | 490万円 |
相続税の計算方法<4ステップ>

この章では、相続税の計算方法を解説します。
1.課税価格を計算する
まずは、死亡した人の財産をすべて明らかにし、課税価格を計算します。
課税価格とは、相続税の対象となる財産から死亡した人の債務と葬式費用を差し引いた金額のことです(正味の遺産額)。
相続税の対象となる財産は、以下を参考にしてください。
| ・被相続人が死亡時に所有していた財産 ・被相続人の死亡によって取得した財産 ・相続時精算課税を適用した贈与財産(贈与時の価額) ・相続開始前3~7年以内の贈与財産 |
▼計算上の注意点
| ・小規模宅地等の特例を適用した財産がある場合、適用後の金額を加算する ・死亡した人の生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産に該当する ・生命保険金や死亡退職金がある場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた金額を加算する |
2.課税遺産総額を計算する
次は、1の課税価格をもとに課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額のことです。
ここからは、以下の想定で解説します。
| 課税価格:1億円 法定相続人:2人(配偶者と子ども1人) |
法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
| 3,000万円+600万円×2=4,200万円 |
1の課税価格から基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額は5,800万円となります。
| 1億円-4,200万円=5,800万円 |
3.相続税の総額を計算する
次は、2の課税遺産総額を法定相続分で分けたとして、相続税の総額を計算しましょう。
法定相続分は、以下の割合に定められています。
▼法定相続分の割合
| 配偶者のみ | 1 |
| 子どものみ | 2人以上の場合は全員で1 |
| 配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者/2分の1 子ども(全員で)2分の1 |
| 配偶者と父母 または祖父母が相続人のケース | 配偶者/3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者/4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
2の課税遺産総額が5,800万円で、法定相続人が2人(配偶者と子ども1人)の場合、法定相続分は配偶者も子どもも2,900万円です。
| 配偶者 | 5,800万円×2分の1=2,900万円 |
| 子ども | 5,800万円×2分の1=2,900万円 |
相続税の速算表で各法定相続人の相続税額を確認し、合計すると相続税の総額は770万円となります。
| 配偶者 | 2,900万円×15%-50万円=385万円 |
| 子ども | 2,900万円×15%-50万円=385万円 |
| 相続税の総額 | 385万円+385万円=770万円 |
▼相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる 取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各法定相続人の納税額を計算する
次は、3の相続税の総額をもとに各法定相続人の納税額を計算します。
3では法定相続分で分けたと想定しているため、実際に相続する割合で計算しましょう。
仮に1億円の遺産を配偶者が60%、子どもが40%の割合で分けたとすると、各法定相続人の納税額は以下に変わります。
| 配偶者 | 770万円×60%=462万円 |
| 子ども | 770万円×40%=308万円 |
なお、適用できる控除額があれば納税額から差し引きましょう。
配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、最終的に納税額は0円となります。
相続税を軽減できる特例・控除は、次章で解説します。
相続税を軽減できる主な特例・控除一覧

相続税の特例・控除を有効活用することで、税額を軽減できます。
主なものは、以下の通りです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の宅地等(土地・権利)を相続した場合に、宅地等の価額を最高400㎡の80%まで減額できる制度のことです。
国税庁:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、死亡した人の配偶者は法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度のことです。
未成年者控除
未成年者控除とは、法定相続人が未成年の場合に以下の金額を控除できる制度のことです。
| 未成年者控除の控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
障害者控除
障害者控除とは、法定相続人が85歳未満の障害者の場合に以下の金額を控除できる制度のことです。
| 障害者控除の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
国税庁:No.4167 障害者の税額控除
相次相続控除
数次相続控除とは、死亡した人が今回の相続が開始される前の10年以内に相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度のことです。
国税庁:No.4168 相次相続控除
外国税額控除
外国税額控除とは、国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されている場合、二重課税を防ぐために一定の金額を控除できる制度のことです。
農地等の納税猶予の特例
農地等の納税猶予の特例とは、死亡した人が生前に農業を営んでおり、相続した農地等で農業を継続する場合に一定の相続税額の納税が猶予される制度のことです。
国税庁:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
国税庁の税額計算シミュレーションも便利!
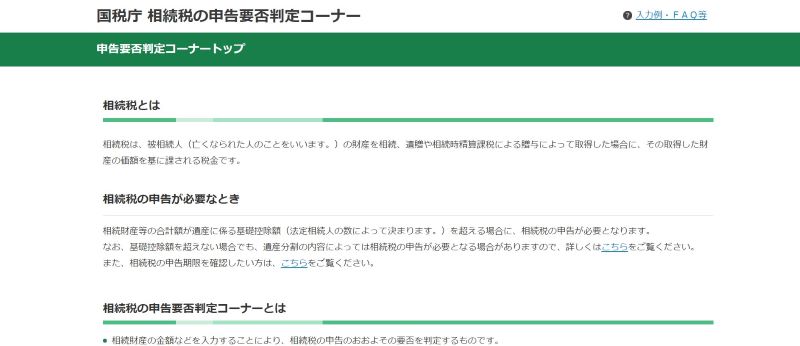
引用:国税庁
国税庁が公開している「相続税の申告要否判定コーナー」では、申告要否の判定だけでなく税額計算シミュレーションも行えます。
自身で計算する必要がないため、おおよその相続税額を把握したい場合にも便利です。
ただし、あくまで目安で正確な税額を計算するものではない点に注意してください。
【Q&A】相続税に関するよくある質問

最後に、相続税のよくある質問にお答えします。
相続税額の2割加算とは?
相続税額の2割加算とは、相続人が死亡した人の配偶者や一親等の血族でない場合に相続税額の2割が相続税額に加算される制度のことです。
たとえば、以下の人が2割加算の対象となります。
| ・死亡した人の孫(代襲相続の場合は加算されない) ・死亡した人の兄弟姉妹 ・死亡した人の甥・姪 |
詳細は、国税庁のホームページで確認できます。
国税庁:No.4157 相続税額の2割加算
相続税の税率は?
相続税の税率は、遺産総額ではなく法定相続分で取得した金額によって変わります。
| 法定相続分に応ずる 取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税はいくらからかかる?
相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えたらかかります。
遺産総額も基礎控除額も家庭によって異なるため、一概には言えません。
| 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
詳しくは、以下の記事で解説しています。
相続税がかかる基準を税理士が解説
相続税のお困りごとは税理士法人吉本事務所へ

相続税のお困りごとは、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
相続専門の税理士が、相続税の節税から申告まで相続税全般のご相談・手続きに対応いたします。
相続が発生すると、相続税に対して大きな不安を感じておられる方が少なくありません。
当事務所はどのようなご相談にも親身に対応いたしますので、以下のようなお悩みがございましたらぜひ一度、税理士法人吉本事務所へお気軽にお問い合わせください。
| ・相続税がかかるかどうか ・かかる場合はどれくらいの額になるのか ・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか ・相続の手続きはどのように進めればよいか ・相続税の申告まですべて任せたい ・相続税の税務調査に不安がある ・相続税を現金で納付するのが難しい |
当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから

まとめ
おおよその相続税額を知りたい場合は、相続税の早見表を参考にしましょう。
遺産総額や家族構成によって相続税額が変わるため、自身の状況に適した早見表を参考にしてください。
正確な税額が知りたい場合や節税のアドバイスを受けたい場合は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
