【税理士監修】現金にかかる相続税はいくら?相続税対策に有効な生前贈与や注意点も解説
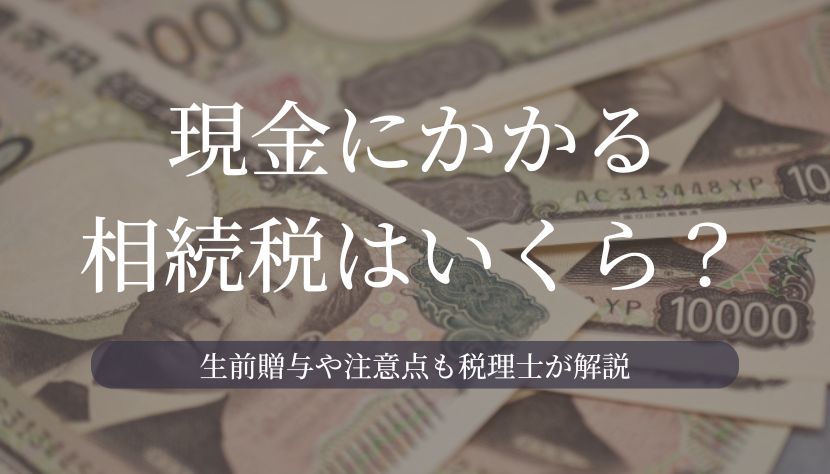
現金は他の財産と比べて遺産分割がしやすかったり使い道が多かったりなどのメリットがありますが、額面が相続税の対象になります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかるため、相続税対策の検討も必要です。
本記事では、現金にかかる相続税の計算方法や相続税対策を中心に解説します。
これから現金を相続する方も、生前贈与を検討している方も、ぜひ参考にしてください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
現金の相続で相続税がかかるケース
相続が発生すると、死亡した人(被相続人)の財産のすべてが相続財産として相続税の対象になります。
もちろん現金も財産に含まれ、被相続人の財布に入っているものから被相続人がタンスの中に貯めているものまで、すべての現金が相続財産になります。
とはいえ、相続税は必ずしもかかる税金ではなく、相続財産の合計額から基礎控除額を超えた場合に、超えた金額に対してかかります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません(無税)。
基礎控除額は相続財産の合計額から差し引ける金額を差し、計算方法は以下の通りです。
| 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
なお、法定相続人は財産を相続する権利がある人を指し、民法で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人で、他の人は以下の通りに順位の高い人から法定相続人になります。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
相続税の基礎控除を税理士が詳しく解説
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額の一覧表です。
法定相続人の数によって基礎控除額が変わります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
現金にかかる相続税の計算方法

前提として、相続税は相続財産の合計額を基準に計算するため、現金にかかる相続税だけを分けて計算することはできません。
たとえば、1億円の現金と5,000万円の土地を相続する場合、合計した1億5,000万円が計算の基準になります。
なお、現金以外の建物、土地、有価証券などの財産は、相続税評価額(相続税を計算するための財産の価額)を先に把握しなければ、相続税は計算できません。
ここからは、計算手順のイメージとして1億円の現金を相続した場合の相続税の計算方法を解説します。
| 法定相続人 | 3人 (配偶者と子ども2人) |
| 相続財産 | 1億円 |
1.課税価格を計算する
被相続人の債務と、相続人が負担した葬式費用は相続財産から差し引くことができ、残った金額が相続税の対象になります。
| 相続財産-(債務+葬式費用)=課税価格 |
今回は例として、借入金が1,000万円、葬式費用が200万円とすると、課税価格は8,800万円になります。
| 課税価格 | 1億円-(1,000万円+200万円) =8,800万円 |
2.課税遺産総額を計算する
先述の通り、相続税は基礎控除額を超えた場合にかかるため、次は基礎控除額を計算しましょう。
1から基礎控除額を差し引き、残った金額に相続税がかかります。
| 課税価格-基礎控除額=課税遺産総額 |
法定相続人が3人の場合は基礎控除額が4,800万円のため、今回の例では4,000万円に相続税がかかることになります。
| 課税遺産総額 | 8,800万円-4,800万円 =4,000万円 |
なお、課税遺産総額が0円またはマイナスになれば相続税はかかりません。
3.相続税の総額を計算する
次は、2を法定相続分の割合で分割し、仮の相続税額を計算しましょう。
| ①課税遺産総額×法定相続分の割合=相続人の相続分 ②相続人の相続分×税率-控除額=相続人の仮の相続税額 |
※法定相続分の割合、税率、控除額は後述の表を参照
法定相続分は遺産分割の基準になる割合を差し、民法で定められています。
法定相続分の割合で分割すると、以下がそれぞれの相続分になります。
| 配偶者の相続分 | 4,000万円×2分の1 =2,000万円 |
| 子ども1人あたりの相続分 | 4,000万円×4分の1 =1,000万円 |
相続人の相続分に応じた税率と控除額を使って計算すると、以下が相続人の仮の相続税額になります。
| 配偶者の 仮の相続税額 | 2,000万円×15%-50万円 =250万円 |
| 子ども1人あたりの 仮の相続税額 | 1,000万円×10% =100万円 |
全員の仮の相続税額を合計すれば、相続税の総額を計算できます。
| 相続税の総額 | 250万円+100万円+100万円 =450万円 |
▼法定相続分の割合
| 配偶者と子どもが 相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
| 配偶者と父母が 相続人のケース | 配偶者3分の2 父母(2人の場合は合わせて)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が 相続人のケース | 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上の場合は全員で)4分の1 |
▼相続税の税率
| 法定相続分に応ずる 取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.相続人ごとの相続税額を計算する
最後に、実際の相続分で相続税額を計算しましょう。
| 相続税の総額×実際の相続分=各相続人の相続税額 |
実際の相続分は家庭によって変わるため、今回の例では法定相続分で相続したとすると、以下が相続人ごとの相続税額になります。
| 配偶者の相続税額 | 450万円×2分の1 =225万円 |
| 子ども1人あたりの相続税額 | 450万円×4分の1 =112万5,000円 |
厳密には、被相続人の配偶者は「配偶者の税額軽減」を使えるため、配偶者の相続税額は0円になります。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

現金の相続税対策には生前贈与が有効
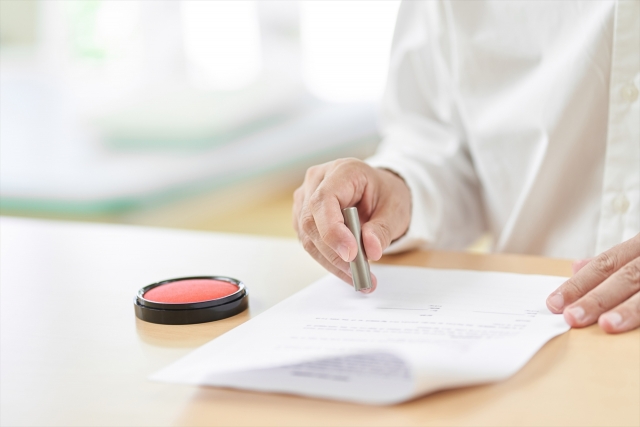
現金にかかる相続税を少しでも減らすには、生前贈与で将来の相続財産を少なくすることが重要です。
相続税は相続財産の合計額を基準に計算することから、将来の相続財産を少なくすれば相続税を減らせます。
ただし、贈与にも贈与税がかかる場合があるため、以下のような贈与税の非課税枠を活用しましょう。
ここからは、贈与税の非課税枠を順に解説します。
なお、そもそも相続税がかからない場合は、生前贈与による節税効果はありません。
1.贈与税の基礎控除を使う
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1月1日から12月31日までの1年間で贈与した金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(暦年課税)。
子どもや孫に110万円の贈与を何度も繰り返し、時間をかけることで税金の負担なく財産を渡せます。
ただし、税務署に定期贈与(一定の期間に一定の金額を贈与すること)と判断されないように注意が必要です。
詳しくは、後で解説します。
2.生活費や教育費を贈与する
扶養義務者からの生活費や教育費の贈与は、110万円の基礎控除とは別で非課税になるため、必要な金額であれば贈与税はかかりません。
ただし、非課税の対象は必要な都度の贈与に限られており、仮に親が子どもに1年分の生活費として200万円を仕送りしたとすると贈与税がかかります。
また、生活費として渡した200万円が貯金されていたり他の用途に使われていたりした場合も贈与税がかかります。
生活費や教育費を贈与するときは、お金の流れがわかるように専用の口座を使って入出金することをおすすめします。
3.教育資金の一括贈与の特例を使う
父母(または祖父母)が30歳未満の子ども(または孫)に教育資金を贈与した場合に、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
先述の必要な都度の贈与ではなく、一括で贈与しても非課税になります。
| 教育資金の例 入学金、入園料、授業料、保育料、施設設備費、入学・入園の試験料 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費、習い事の費用 など |
ただし、契約期間中に贈与者が死亡したり契約終了時に資金が残っていたりする場合、相続税または贈与税がかかるため、特例を使うなら早いうちに使いきれる金額だけを贈与しましょう。
この特例を使うには、専用の口座を開設し、口座を開設した金融機関に非課税申告書の提出が必要です。
4.結婚・子育て資金の一括贈与の特例を使う
父母(または祖父母)が18歳以上50歳未満の子ども(または孫)に結婚・子育て資金を贈与した場合に、1,000万円までは贈与税が非課税になる制度です。
| 結婚・子育て資金の例 挙式・婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) 家賃・敷金等の新居費用(一定の期間内に支払われるもの) 不妊治療費、妊婦健診費用、分娩費用、産後ケアの費用 子どもの医療費、保育料(ベビーシッター代を含む)など |
教育資金の一括贈与の特例と同じで、契約期間中に贈与者が死亡したり契約終了時に資金が残っていたりする場合、相続税または贈与税がかかります。
この制度を使うには、専用の口座を開設し、口座を開設した金融機関に非課税申告書の提出が必要です。
5.住宅取得等資金の贈与の特例を使う
父母(または祖父母)が18歳以上の子ども(または孫)に自宅を買うための資金を贈与した場合に、最高1,000万円までは贈与税が非課税になる制度です。
ケースにより非課税の範囲が異なり、省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、該当しない場合は500万円までとなります。
また、贈与を受けられる人には細かい要件があるため、使い方を誤らないように税理士へ相談することをおすすめします。
6.相続時精算課税制度を使う
原則として60歳以上の父母(または祖父母)が18歳以上の子ども(または孫)に財産を贈与した場合に選べる制度で、110万円の基礎控除額+2,500万円までは贈与税が非課税になります。
ただし、贈与した人が死亡したときは、この制度を使って贈与した財産の価額から年間110万円の基礎控除額分を差し引いた金額が相続財産に加算されます。
この制度を使うには、税務署に相続時精算課税選択届出書の提出が必要で、一度選択すると取り消せないため、税理士に相談したうえで判断することをおすすめします。
7.贈与税の配偶者控除を使う
婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅または自宅を買うための資金を贈与した場合に、110万円の基礎控除額+最高2,000万円までは贈与税が非課税になる制度です(おしどり贈与)。
夫婦間で財産を分散させるという意味では節税効果が得られる場合がありますが、そもそも配偶者は1億6,000万円までは相続税がかかりません。
この特例を使うべきかどうかは、配偶者の財産の状況や将来を見据えて慎重に検討したほうがよいでしょう。
現金を生前贈与するときの注意点

現金を生前贈与するときは、以下4点に注意してください。
贈与の事実を証明できる証拠を残す
贈与は財産をあげる人ともらう人が意思表示をすれば成立しますが、証拠として贈与契約書を交わしましょう。
税務署に贈与の事実を証明できなければ、相続財産として加算される可能性があるためです。
贈与契約書には、誰が、誰に、いつ、何を贈与するかを明記し、両者の署名捺印を書面に残します(できれば公証人役場で確定日付をもらう)。
また、現金を贈与するときは、手渡しではなく銀行振込で渡しましょう。
定期贈与は合計額に贈与税がかかる
贈与税の基礎控除を使って贈与を繰り返すときは、税務署に定期贈与と判断されないように注意が必要です。
定期贈与とは、毎年、一定の時期に一定の金額を贈与することを指します。
たとえば、1,000万円を10回に分けて、毎年100万円を贈与したとします。
税務署に「最初から1,000万円を贈与すると両者で約束されていた」と判断されると、1,000万円から110万円の基礎控除額を差し引いた890万円に贈与税がかかります。
定期贈与を回避するには、贈与するごとに贈与契約書を作成し、贈与する時期や金額を一定にしないなどの対策がよいでしょう。
名義預金は相続財産として加算される
名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金を指します。
たとえば、祖父が孫の名義で口座を開設し、祖父が自分のお金を孫のために預金しているケースなどがあります。
税務署に名義預金と判断されると相続財産として加算されるため、思い当たる場合は贈与契約書を作成したり名義人に口座を管理させたりなどの対策が必要です。
名義預金は以下の記事で詳しく解説しています。
名義預金の判断基準や対策を税理士が解説
生前贈与加算の対象になる場合がある
生前贈与加算とは、相続が発生する前の3〜7年以内に贈与した財産が相続財産として加算されることを指します。
加算の対象になると、贈与税は非課税でも相続税を減らすという意味では節税効果が薄まるため、生前贈与は早いうちに計画し、実行することをおすすめします。
相続税対策には不動産を活用するのも一つの手

相続税を減らすには、不動産を活用するのもよいでしょう。
相続税を計算するための相続税評価額が関係しており、現金の相続税評価額は額面の通りですが、不動産の相続税評価額は一般的に時価の80%になります。
言い換えると、1億円の現金を相続すると1億円に対して相続税がかかり、1億円の不動産を相続すると8,000万円に対して相続税がかかるイメージです。
ここからは、現金と土地の相続税を比較してみましょう。
※あくまでイメージを掴むための簡単なシミュレーションです。
現金と土地の相続税を比較
法定相続人は1人として、1億円の現金を相続した場合と、1億円の現金で土地を買って相続した場合の相続税を計算します。
1億円の現金を相続した場合
法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。
1億円から基礎控除額を差し引くと6,400万円が残るため、相続分に応じた税率と控除額を使って計算すると、相続税額は1,220万円になります。
| 1億円-3,600万=6,400万円 6,400万円×税率30%-控除額700万円=1,220万円 |
1億円の現金で土地を買って相続した場合
土地の相続税評価額は一般的に時価の80%になるため、8,000万円が相続税の対象になります。
8,000万円から基礎控除額を差し引くと4,400万円が残るため、相続分に応じた税率と控除額を使って計算すると、相続税額は680万円です。
| 8,000万円-3,600万=4,400万円 4,400万円×税率20%-控除額200万円=680万円 |
簡単なシミュレーションではありますが、財産の種類が変わることで相続税額は540万円もの差が出ました。
なお、一定の土地には小規模宅地等の特例を使えるため、さらに相続税を減らせる場合もあります。
とはいえ、一概に現金よりも不動産のほうがよいとは言えないため、税理士と相談しながら検討することをおすすめします。
不動産を活用した相続税対策は、以下の記事で詳しく解説しています。
不動産を活用した3つの相続税対策を税理士が解説
【Q&A】現金の相続に関するよくある質問

最後に、現金の相続に関するよくある質問にお答えします。
現金にかかる相続税はいくらまで無税?
現金を含め、相続財産の合計額が基礎控除額を超えなければ相続税は無税です。
基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。
| 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
現金は申告しなくてもバレない?
タンス預金のような記録がない現金でも、税務署に隠し通すことはできません。
税務調査では調査官に徹底的に調べられるため、申告していないことがバレると、延滞税や加算税などのペナルティが課される場合があります(追徴課税)。
相続するなら現金と不動産のどちらが得?
不動産を活用することで相続税を減らせる場合がありますが、必ずしも不動産が得とは言い切れません。
節税目的のみで不動産を買っただけでは損するリスクがあるため、必ず税理士に相談してください。
相続税のお悩みは税理士法人吉本事務所へ

・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
・どのような方法で生前贈与するべきか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
当事務所の相続専門の税理士は相続税対策を得意とし、相続税への不安や心配を少しでも解消できるように、相続税全般のご相談・ご依頼をお受けしています。
相続が発生する前から発生後まで、どのようなケースでもお任せください。
600件を超える申告実績と長年の経験を強みに、お客様のご状況に合わせた最善策をご提案いたします!
相続税のご相談は初回無料でお受けしているので、些細なことでも安心してお聞かせください。
当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから
\相続税のご相談は初回無料で承っております/

まとめ
現金を含めた相続財産の合計額が基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
正確な税額を知るためには、すべての財産の相続税評価額を把握することから始まるため、相続専門の税理士に相談するとよいでしょう。
なお、相続が発生する前であれば、生前贈与で相続税を減らせる場合があります。
早いうちに計画し、積極的に実行することをおすすめします。
