死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税!相続税がかかる理由や計算例も税理士が解説
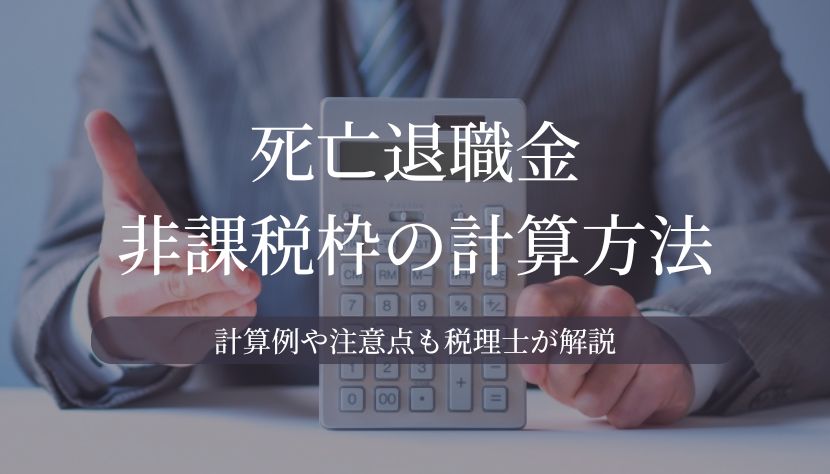
結論から言うと、死亡退職金は相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
ただし、受け取った全額ではなく「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本記事では、死亡退職金に相続税がかかる理由や、非課税枠の計算方法を中心にわかりやすく解説します。
相続税がかかる場合とかからない場合の計算例も用意しているので、判断に悩む方はぜひお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
死亡退職金には相続税がかかる
被相続人(亡くなった人)が死亡してから3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税法で相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
死亡退職金は被相続人の死亡の事実によって支払われるものであり、被相続人から相続した財産と実質は変わらないことが理由です。
なお、以下のようなものも死亡退職金とみなされます。
| ・生前に退職していたが、死亡してから3年以内に支給が確定したもの ・退職金という名目ではないが、実質は変わらない金銭、現物、権利など |
本来の相続財産(民法の相続財産)ではないものの、相続税法で相続財産とみなされるものを「みなし相続財産」と呼びます。
死亡退職金の受取人は一般的には配偶者に設定されていますが、勤務先の規定によるため、詳細は勤務先に確認するとよいでしょう。
相続財産にはならない
先述の通り、被相続人の遺族が受け取る死亡退職金はみなし相続財産になりますが、これは相続税法の取り扱い方であり、本来の相続財産(民法の相続財産)にはなりません。
簡単に説明すると「相続税を計算するときは相続財産とみなして取り扱いますよ」という意味で、実際は受取人の固有の財産であるため、原則として遺産分割の対象にもなりません。
死亡退職金の非課税枠の計算方法
死亡退職金の非課税枠は法定相続人の数で決まり、法定相続人が1人であれば500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円と、法定相続人1人あたり500万円が加算されます。
| 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 |
死亡退職金が非課税枠以下の場合は全額が非課税になり、死亡退職金に相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 死亡退職金の非課税枠 |
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
| 5人 | 2,500万円 |
法定相続人の範囲
死亡退職金の非課税枠を計算するときは、法定相続人の範囲や数え方を誤らないように注意しましょう。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
また、相続税法では意図的に法定相続人の数を増やす(=非課税枠を増やす)ことを防ぐために、以下のルールがあります。
| ・相続放棄した人がいても法定相続人として数える ・被相続人の養子は法定相続人に含める数に制限がある ※実子がいる場合→1人、実子がいない場合→2人 |
次章では、死亡退職金の非課税枠の計算方法をシミュレーションしてみましょう。
計算例①死亡退職金に相続税がかかるケース
ここからは、以下の前提で死亡退職金に相続税がかかるケースを計算していきます。
| 死亡退職金 | 2,000万円 |
| 受取人 | 妻 |
| 法定相続人 | 妻と子ども2人の計3人 |
法定相続人の数が3人とすると、死亡退職金の非課税枠は1,500万円です(500万円×3人=1,500万円)。
受け取った死亡退職金は2,000万円のため、非課税枠を差し引いた残りの500万円が相続税の対象になります(2,000万円-1,500万円=500万円)。
なお、相続税は死亡退職金の500万円を含めた、相続財産の合計額を基準に計算します。
そもそも相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため、死亡退職金の非課税枠を超えたからといって必ずしも相続税がかかるとは限りません。
相続税の計算方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税の計算方法や注意点を税理士が解説
計算例②死亡退職金に相続税がかからないケース
次は、以下の前提で死亡退職金に相続税がかからないケースを計算していきます。
| 死亡退職金 | 1,500万円 |
| 受取人 | 妻 |
| 法定相続人 | 妻と子ども3人の計4人 |
法定相続人の数が4人とすると、死亡退職金の非課税枠は2,000万円となります(500万円×4人=2,000万円)。
受け取った死亡退職金は1,500万円で非課税枠以下になるため、このケースでは死亡退職金に相続税はかかりません。
ただし、相続税は相続財産の合計額を基準に計算するため、最終的に相続税がかかるかどうかは別で計算が必要です。
正確な判断は、税理士に相談することをおすすめします。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

死亡退職金を受け取るときの注意点

死亡退職金を受け取るときは、以下3点に注意しましょう。
死亡退職金に所得税がかかる場合がある
被相続人が死亡してから3年より後に死亡退職金の支給が確定した場合は、相続税ではなく一時所得として所得税の対象になります。
まとめると以下の通りです。
| 退職金の支給が確定した時期 | かかる税金 |
| 被相続人が死亡してから3年以内 | 相続税 |
| 被相続人が死亡してから3年より後 | 所得税 |
なお、生前に本人が受け取る通常の退職金は所得税の対象で、退職金から差し引かれて支給されます。
死亡退職金と生命保険金の非課税枠は併用できる
死亡保険金と同じく、相続財産にみなされる生命保険金にも以下の非課税枠があります。
| 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 |
死亡退職金と生命保険金の非課税枠は併用できるため、両方を受け取った場合はそれぞれに非課税枠を使いましょう。
なお、非課税枠の計算方法も同じです。
相続放棄すると非課税枠は使えなくなる
死亡退職金は本来の相続財産(民法の相続財産)ではないため、相続放棄しても受け取ることができる一方、相続放棄すると非課税枠は使えなくなります。
さらに注意点として、非課税枠は使えなくなりますが、非課税枠を計算するときは法定相続人として数える必要があることも覚えておきましょう。
まとめると以下の通りです。
| ・死亡退職金は相続放棄しても受け取れる ・相続放棄すると死亡退職金の非課税枠は使えなくなる ・非課税枠を計算するときは法定相続人に相続放棄した人を含める |
死亡退職金と弔慰金の違い
弔慰金とは、会社から遺族へ被相続人の弔う意味で支払われる金銭のことで、主に遺族の生活を保障するための死亡退職金とは意味合いが違います。
また、死亡退職金は非課税枠の一定の金額しか非課税になりませんが、弔慰金は原則として非課税です。
ただし、会社役員が死亡したような場合で、弔慰金として多額の金銭が遺族に支給されるケースが見受けられたことにより、以下の金額を超える部分の弔慰金は死亡退職金として取り扱われ、相続税の対象になります。
| 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合 | 普通給与の3年分に相当する額 |
| 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合 | 普通給与の半年分に相当する額 |
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額のこと。
会社経営者は死亡退職金で相続税対策ができる
相続発生前であれば、会社経営者は死亡退職金や弔慰金を活用することで相続税対策ができます。
先述の通り、死亡退職金や弔慰金には非課税枠があるほか、未払金として計上すると会社の純資産から差し引くことができ、被相続人が保有する自社株の評価額を下げられるためです(純資産価額方式で評価する場合)。
ただし、死亡退職金は勤続年数や功績倍率などを踏まえて計算しなければならず、高額すぎると税務署に指摘される場合があります。
また、あらかじめ規定を作成したり今後の経営に影響を与えないように生命保険の加入を検討したりなど事前の対策も必要になるので、税理士へ早いうちに相談するとよいでしょう。
相続税に関するご相談は税理士法人吉本事務所へ

・何が相続税の対象になるかわからない
・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、一人ひとりのお客様のご事情やご要望に合わせてきめ細かく、親身に相続税全般のご相談をお受けしております。
また、長年の経験と最新の知識を活かした相続税対策に強みがあり、できる限りお客様の負担を軽減できるよう個別にご提案いたします。
なお、相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもまずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから
\相続税のご相談は初回無料で承っております/

まとめ
死亡退職金はみなし相続財産として取り扱うため、相続税の対象になります。
ただし、法定相続人が1人の場合は500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円と、法定相続人1人あたり500万円の金額は非課税です。
| 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 |
なお、相続税は財産ごとにかかるわけではなく、死亡退職金を含めた相続財産の合計額を基準に計算する必要があります。
最終的に相続税がかかるかどうかの判断に悩む場合は、税理士に相談すると安心できるでしょう。
